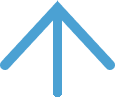教室紹介
主任教授挨拶
肝胆膵消化器病学教室について
消化器内科は食道、胃、小腸、大腸、膵臓、胆のう、肝臓の7臓器を扱う広範な領域です。当院の消化器内科は「肝胆膵消化器病学」および「消化器内科学」の二つの部門が担当し、すべての消化器疾患に対応可能とすることに努力しております。 肝胆膵消化器病学では消化管グループ(食道・胃・小腸・大腸)、肝グループ(肝臓)、胆膵グループ(胆嚢/胆道系・膵臓)の3グループに分かれることて、互いに連携を取りながら大学病院で求められる専門・高度な医療の提供に努めています。また様々な研究活動も行い、論文発表や国内外の学会での発表を通じて、日本・世界へ情報発信を行っています。
主任教授挨拶

米田 正人
(よねだ まさと)
横浜市立大学大学院医学研究科 肝胆膵消化器病学主任教授
横浜市立大学附属病院 消化器内科診療部長
横浜市立大学附属病院 国際臨床肝疾患センター センター長
肝胆膵消化器病学教室 第二代主任教授就任にあたって
このたび、横浜市立大学大学院医学研究科 肝胆膵消化器病学教室の第二代主任教授を拝命いたしました米田正人と申します。
初代教授である中島淳先生のもと、臨床・教育・研究の各分野において着実に礎を築いていただいた本教室を引き継ぐことは、誠に光栄であるとともに、その責任の重さを深く感じております。
本教室は、旧第3内科(消化器内科・糖尿病内分泌内科領域)から発展した分子消化管内科学の流れを汲み、横浜市立大学附属病院において、肝疾患、胆膵疾患、消化管疾患の包括的な診療体制を整備してまいりました。若い教室ではありますが、これまでに多くの大学院生や博士を輩出し、神奈川県内外の医療現場にとどまらず、肝臓・胆膵・消化管領域における診療ガイドラインの策定にも委員として参画するなど、国内外で指導的立場で活躍している医師も数多くおります。
今後は、こうした貴重な伝統を大切に継承しながら、診療のさらなる質の向上、次世代を担う若手医師の育成、そして世界に発信できる臨床研究の推進に全力で取り組んでまいります。
消化器病学におけるパラダイムシフトと大学病院の新たな使命
昨今、消化器病学の各領域では、診断や治療の枠組みそのものが時代とともに大きく変容する“パラダイムシフト”が進行しています。とりわけ、免疫チェックポイント阻害薬やバイオ製剤の開発は、これまで治療が困難とされてきた疾患に対する診療戦略を根本から変革しつつあり、現在では、その高い治療効果と引き換えに生じうる副作用への対策や、個別化医療の視点を取り入れた治療選択が重要な課題となっています。
肝疾患領域においては、かつて肝生検を中心としていた診断体系が、現在では血液バイオマーカーやエラストグラフィといった非侵襲的診断法(NIT)を基軸とする体制へと大きく転換しました。こうした新たな診断技術は、かかりつけ医と専門医が共通の“言語”を持ちやすくなる基盤を築き、患者さんを中心に据えた真の医療連携を可能にしています。私はライフワークとして、非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)、現在では代謝機能障害関連脂肪性肝疾患(MASLD)を中心とした肝疾患の臨床研究に取り組んでまいりました。MASLD領域ではNITの発展が著しく、FIB-4 indexや肝硬度測定値などのバイオマーカーが、紹介・逆紹介の判断や治療効果の評価指標として活用され、地域全体で標準的な診療体制の構築が進みつつあります。
胆膵領域においても、超音波内視鏡(EUS)や内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)といった技術革新により、難治性胆道狭窄や早期膵がんといった疾患の診断精度が飛躍的に向上しています。さらにinterventional EUSによる胆道治療など、低侵襲で高度な治療手技が可能となっており、診断と治療の一体化が実現しつつあります。また、AIや画像診断支援システムの導入、消化器内視鏡センターの機能強化などにより、地域における高度医療の“均てん化”も現実のものとなってきました。
現代の消化器病学は、まさに転換期を迎えています。MASLDのような疾患概念の再定義、個別化医療の進展、内視鏡技術の革新に加え、デジタルヘルスやAIの活用が進むことで、診療・研究のあらゆる領域においてパラダイムシフトが加速しています。同時に、医療界全体としても、働き方改革やチーム医療の推進といった構造的変革が求められており、もはや従来の「決まりを守る」だけでは対応しきれない時代に突入しています。むしろ、柔軟な発想と行動力、そして“今ある常識を問い直す姿勢”こそが、これからの大学病院や学術機関において強く求められていると感じています。私は、このような変化の時代にこそ、学問と医療の価値を再定義し、それを次世代に継承していく責任があると考えています。
本教室には、消化管、胆膵、肝の各領域において専門性と情熱を兼ね備えた優秀なスタッフが揃っており、内視鏡、画像診断、肝移植、先進的な内視鏡治療、難病診療など、大学病院ならではの高度な医療を提供しています。さらに、診療にとどまらず、医学部教育や大学院教育、そして地域医療への貢献にも今後一層注力してまいります。特に、診断が困難な疾患や治療法が未確立の病態に果敢に挑み、現場の疑問から出発する“リバーストランスレーショナル”な臨床研究を推進し、私たち自身の手で未来の教科書をつくっていきたいと考えております。
略歴
- 2001年 横浜市立大学医学部卒業
- 2004年 横浜市立大学大学院医博士課程卒業
- 2005年 横浜市立大学附属病院消化器内科助手
- 2007年 横浜市立大学附属病院助教
- 2013年10月-2016年2月 University of Miami Miller School of medicineに留学
- 2016年3月 横浜市立大学附属病院 肝胆膵消化器病学 講師
- 2019年4月 横浜市立大学附属病院 国際臨床肝疾患センター 准教授
- 2023年4月 横浜市立大学附属病院 国際臨床肝疾患センター センター長
- 2025年8月 横浜市立大学大学院医学研究科 肝胆膵消化器病学 主任教授
専門領域
- 肝疾患全般、とくに代謝機能障害関連脂肪性肝疾患(MASLD)
- 非侵襲的診断方法、とくに超音波エラストグラフィ,MRエラストグラフィ
- 日本消化器病学会・日本肝臓学会 NAFLD/NASH診療ガイドライン作成委員
- 日本消化器病学会・日本肝臓学会 MASLD診療ガイドライン作成委員
- アジア太平洋肝臓学会(APASL)MAFLD診療ガイド作成共著者
- 日本肝臓学会・日本成人先天性疾患学会/日本小児循環器学会 FALD診療のてびき 執筆分担者
- 日本消化器病学会指導医、日本肝臓学会指導医、日本消化器内視鏡指導医、総合内科専門医
- 日本肝臓学会欧文誌編集委員
- 神奈川県内科医学会 肝・消化器疾患対策委員会 委員
受賞歴
- 2003年 第13回ヨーロッパ消化器病学会優秀演題賞,Travel Grant Award
- 2007年 日本肝臓学会優秀演題賞
- 2007年 横浜市立大学医学奨励賞
- 2008年 日本消化器病学会優秀演題賞
- 2008年 横浜市立大学Clinical Research Fellow賞
- 2009年 横浜市立大学Clinical Research Fellow賞
- 2010年 Journal of Gastroenterology High Citation Award受賞
- 2011年 Journal of Gastroenterology High Citation Award受賞(2回目)
- 2013年 日本肝臓学会High citation award受賞
- 2023年 日本医療機器学会 青木賞受賞
- 2024年 横浜市立大学医学会 医学会賞受賞
- 2024年 公立大学法人横浜市立大学 令和5年度理事長・学長表彰 教員部門「優秀賞」受賞
- 2024年 Journal of Gastroenterology High Citation Award受賞(3回目)
初代主任教授挨拶

中島 淳
(なかじま あつし)
横浜市立大学大学院医学研究科
肝胆膵消化器病学教室初代主任教授
(現在:国際医療福祉大学熱海病院 病院長
国際医療福祉大学 消化器内科統括教授)
根っからの臨床家
横浜市立大学医学部に新しい教室として肝胆膵消化器病学教室の設立に伴い主任教授を拝命いたしました。本教室は10年ほど前に本学医学部の大学院大学化で新設されました分子消化管内科学の流れをくむ教室です。今回大学院のみならず附属病院での診療、医学部での教育や地域貢献を一括しておこなう新教室となりました。分子消化管内科学時代にすでに50名弱の博士を輩出しております。その多くは神奈川県内の多くの病院で臨床医として、大学で教員を行うなどして多方面で活躍されております。新教室設立に伴いまして今後は医学部学生の教育、附属病院での診療、さらに臨床研究や地域貢献に向けてこれまで以上に精一杯頑張る所存でございますのでどうかよろしくご指導いただければと思います。 さて、私は根っからの臨床家であると考えております、できるだけ多くの患者様を拝見させて頂ければと思っておりますし、常に真摯な姿勢で患者様と対峙し、診断や治療がわからないときは徹底して解決しなければと思います。内科医でありますので、それまで診断がつかない患者様の診断、治療ができたときは大変うれしく思います。教室で若手の医師との検討をして日々悩んでおりますが、やはり重要なことは患者様をしっかり診ることではと常々痛感いたします。大学病院ならではの診断、治療の難しい患者様も多いのですが、やはり目の前の患者様から学ばせていただけることが多々あります。教科書や成書を見て分からなくとも目の前の患者様から学んだこと、そこから未来の教科書が生まれるものと考えますし、そう信じて大学病院として求められている診療を進めようと思いまっております。幸い、我々しか診断できない検査や病気がいくつかあり、横浜市内はもとより全国から多くの患者様がいらっしゃっており医者としてうれしい限りです。特に我々が診断基準や治療指針を策定しております慢性特発性偽性腸閉塞症という難病に関しては、国内で唯一の専門拠点として当該疾患の国内での最後の砦になっております。
教室の診療内容
教室の診療内容としましては、肝臓疾患は斉藤聡医師を中心としてウイルス肝炎、肝臓がんなどの患者様を多く診療しております、当院は肝臓移植も行いますのでそのような患者様、劇症肝炎の患者様なども受け入れております。肝臓の病気では、近年我が国で患者が増加している非アルコール性脂肪肝炎(NASH)の臨床および研究も精力的に行っております。これは現在マイアミ大学に留学中の米田医師が大学院時代に研究を始め、現在では国内で有数の診療経験を誇っております。また本年度刊行された日本消化器病学会編集による診療ガイドラインでは、私をふくめ横浜市立大学肝胆膵消化器病学が診断部門を担当させていただきました。膵臓胆道系疾患では内視鏡センター長である窪田医師が中心となって、外科の遠藤教授と極めてスムーズな連携で黄疸などの救急患者や、近年増加してきた膵臓がんの早期発見や診断・治療を行っております。消化管に関しては野中医師を中心に昨年リニューアルしました内視鏡センターのおかげをもちまして、多くの患者様の内視鏡検査・治療を行っております。また遠藤医師を中心に小腸カプセル内視鏡や、最近臨床現場で使えるようになりました大腸カプセル内視鏡など先進医療機器を用いた診療も精力的に行っております。カプセル内視鏡は、多くの医療機関から読影を依頼され診断のサポートを行っておりますし、検査件数は神奈川県最多を誇っております。バルーン内視鏡を用いた診断、治療も積極的に行っており、小腸癌、小腸型のクローン病などこれまで診断が困難とされてきた小腸疾患の早期診断・早期治療にも努めております。
これからも大学病院の責務の一つとして、現在わからない病気の病態や、診断・治療方法の開発など臨床研究を精一杯行いつつ、臨床に還元し高度な診療を行うことで、地域の、また全国の患者様のお役になって生きたいと考えております。
略歴
- 平成元年大阪大学卒業
- 平成2年 ― 4年社会保険中央総合病院内科(高添正和医師)
- 平成3年 ― 茅ヶ崎市立病院 内科
- 平成9年 東京大学第3内科助手(矢崎義雄教授)
- 平成10年ハーバード大学Brigham and Women’s Hospital 客員研究員(Richard S Blumberg教授)
- 平成12年4月横浜市立大学第3内科講師
- 平成12〜15年 ハーバード大学医学部客員准教授
- 平成20年横浜市立大学付属病院消化器内科教授
- 平成26年横浜市立大学大学院医学研究科 肝胆膵消化器病学教室主任教授
専門領域
- 消化管運動異常、とくに慢性特発性偽性腸閉塞、難治性便秘、機能性腹部膨満症
- 肥満と消化器疾患、特に非アルコール性脂肪肝炎(NASH)
- 大腸がんの発がんメカニズム(特にepigeneticな異常)と化学予防
- 小腸疾患の診断と治療、特にleaky gut syndromeやsmall bowel bacterial overgrowth
- 米国消化器病学会フェロー
- 日本消化器病学会指導医、日本肝臓学会指導医、内科学会総合内科専門医、消化器内視鏡学会指導医
- 日本内視鏡学会奨励賞、米国クローン財団リサーチアワード
- 厚生労働省 「我が国における慢性特発性犠牲腸閉塞の疫学・診断・治療の調査研究班」研究代表(班長)(平成21−23年)
- 厚生労働省 「我が国におけるslow transit constipationの疫学・診断・治療の調査研究班」研究代表(班長)(平成26年)
- 科学技術振興機構(JST)産学協同プロジェクトA-ステップ「非アルコール性脂肪肝炎の非侵襲的診断法の開発」プロジェクトリーダー(平成22-24年)
- 日本消化器病学会「肥満と消化器疾患」委員会委員
- 日本消化器病学会 NASH/NAFLDの診療ガイドライン作成委員メンバー
- 日本消化器病学会 慢性便秘の診断と治療の附置研究会 幹事
主な業績
- Higurashi T, Hosono K, Takahashi H, Komiya Y, Umezawa S, Sakai E, Uchiyama T, Taniguchi L, Hata Y, Uchiyama S, Hattori A, Nagase H, Kessoku T, Arimoto J, Matsuhashi N, Inayama Y, Yamanaka S, Taguri M, Nakajima A. Metformin for chemoprevention of metachronous colorectal adenoma or polyps in post-polypectomy patients without diabetes: a multicentre double-blind, placebo-controlled, randomised phase 3 trial. Lancet Oncol. 2016 Apr;17(4):475-83.
- Imajo K, Kessoku T, Honda Y, Tomeno W, Ogawa Y, Mawatari H, Fujita K, Yoneda M, Taguri M, Hyogo H, Sumida Y, Ono M, Eguchi Y, Inoue T, Yamanaka T, Wada K, Saito S, Nakajima A. Magnetic Resonance Imaging More Accurately Classifies Steatosis and Fibrosis in Patients with Nonalcoholic Fatty Liver Disease Than Transient Elastography. Gastroenterology. 2016 Mar;150(3):626-637.e7.
- Yamada E, Inamori M, Uchida E, Tanida E, Izumi M, Takeshita K, Fujii T, Komatsu K, Hamanaka J, Maeda S, Kanesaki A, Matsuhashi N, Nakajima A. Association Between the Location of Diverticular Disease and the Irritable Bowel Syndrome: A Multicenter Study in Japan. Am J Gastroenterol. 2014 Dec;109(12):1900-5.
- Olszak T, Neves J, Dowds M, Baker K, Glickman J, Davidson N, Lin CS, Jobin C, Brand S, Sotlar K, Wada K, Katayama K, Nakajima A, Mizuguchi H, Kawasaki K, Nagata K, Kaser A, Zeissig S, Schreiber S, Müller W, Snapper S, Blumberg R,. Protective mucosal immunity mediated by epithelial CD1d and IL-10. Nature. 2014 May 22;509(7501):497-502.
- Ohkubo H, Kessoku T, Fuyuki A, Iida H, Inamori M, Fujii T, Kawamura H, Hata Y, Manabe N, Chiba T, Kwee TC, Haruma K, Matsuhashi N, Nakajima A, Takahara T. Assessment of Small Bowel Motility in Patients With Chronic Intestinal Pseudo-Obstruction Using Cine-MRI. Am J Gastroenterol. 2013 Jul;108(7):1130-9.
- Imajo K, Fujita K, Nozaki Y, Kato S, Yoneda M, Kirikoshi H, Ikejima K, Watanabe S, Wada K, Nakajima A. Hyperresponsivity to low-dose endotoxin during progressionto nonalcoholic steatohepatitis is regulated by leptin-mediated signaling. Cell Metab. 2012 Jul 3;16(1):44-54.